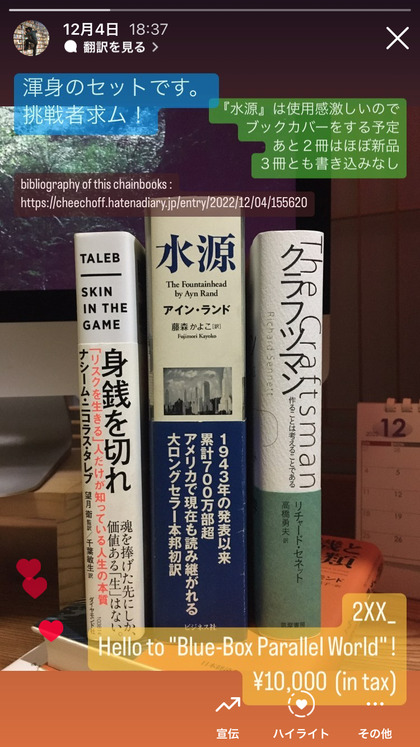オフィスの鎖書在庫棚が何度目かであふれてきたので、
棚の増設ではなく古い在庫を段ボールにしまうという作業を先日始めました。
そのうち、「出品したけど読み直したい本」が一つあるのを見つけて、
というのは棚にはその本のかわりに同サイズの木材を立てていたから気付いたのでした。
その一冊とは『小林秀雄の恵み』(橋本治)で、
読み直すために家に置いていたことを忘れたいたのをこの作業中に思い出した次第で、
早速(読まないとセットを仕舞えないので)読み始めました。
記録によれば初読は10年前の2011年3月ですが、
それから今までの間に何度か頁を開いたような気もします。
さて、読み出せば引き込まれることは(何せ再読だから)わかっていて、
橋本治のことだから読み出せば連想が多々働いて頁を繰る手も止まるとわかっていて、
だからこそ二度目の今回は速読を心がけて読み始めたのですが、
(もともと書き込んであるので、追加の書き込みは商品であれ辞すまいという意識はあったにせよ、)
かつて自分が線を引いた箇所を「なるほど」と思ったり「そうなの?」と思ったり、
しつつも読み飛ばしていたのが、次第に追加の線引きが増えてきて、
話が佳境に(といってまだ2/3過ぎですが)入ったところで、
リアルタイムな出来事との連想が色々繋がってしまい、
腰も痛いので(え?)「これは書かねばなるまい」と思いました。
× × ×
昨日はいつも行っているジム(僕の知る他のどのジムより独自に本棚が充実している)で、
はじめてその本棚の本を少しのあいだ読むことがありました。
降らないと思っていたのに帰り間際、にわか雨がしばらく降ったからです。
内田樹(『憲法の空語を満たすために』)、高村薫(『土の記』)など、
僕自身なかなか親和性の高い種類の本がいくつもある中で、
たしか『あわいの力』は読んだことのある、安田登の本を手に取りました。
「珈琲と本」というテーマだったかのセレクションの一冊で、『イナンナの冥界下り』。
短時間だったのでシュメール語の世界最古(だったかな)のその物語の、
現代語訳を読んだところで本棚になおして昨日は家に帰ったのですが、
記憶に残ったのはその物語ではなくまえがき(か帯文?)の中にあった、
「心の時代」の”次の時代”を探る、といった感じの文言でした。
人間は(シュメールの時代に)心を発見したことで同時に不安も発見してしまった。
心の発見は人間をより豊かにするものでありながら、
不安の増幅は、かつての人間にはなかった負の作用をもたらすものであった。
人の「意識の歴史」は、そのバランスをとろうとぐらぐら揺れ進む時間であったが、
現代は不安の負の作用が極端に増大した時代となってしまった。
そのバランスを取り戻すためには、「心」に代わる新しい「なにか」の探求が必要だ。
まえがきの一節は、たしかそのような内容だった、はず(昨日のことなのにこの曖昧さ)。
所変わって、橋本治の『小林秀雄の恵み』です。
この本は僕にとっては凄すぎて、
今再読すると、かつて自分に大きな影響を与えたであろう箇所が多々あって、
その一つひとつを掘り下げるだけで各々膨大な労力を要するだろう、
ゆえにこの一冊の総括というか全体的な評価なぞできるはずもない、
と読みながら思っていたのでしばらくは何も書くまいと心に固めていたんですが、
つながりが一挙にいくつか生まれて、
それをその瞬間の快感に留めておくことに飽き足らず、
というのは「そのいくつか」を具体的に言葉にしていく作業が、
新たに何かを生むだろうという確信がそばにあったからこそ、
こうして書き始めることになったんですが、
その意志がさっきこれを書く前に、
ブラウザを立ち上げた段階(の表示エラーを解決するという横道作業)で若干挫けました。
しかし、ええ、挫けませんとも。
というわけで、本題。
× × ×
近世という時代は、「神という非合理」などとは言わない。それを言ってしまえば、もう近代である。近世という時代は、非合理かもしれない神を一方に存在させて、その残りを合理性で仕切るという時代なのだ。神という非合理の支配下にあれば中世だが、近世という時代は、かつて支配的だった神をそのままの位置に安置し、距離を置いて隔離する──だから、支配はされないのである。それが近世で、だからこそ近世を登場させるルネサンスの中に、ちゃんと神はいる。神という非合理と、合理性を求める人とが調和的であるのは、神と人とが距離を保ちえた近世の特徴なのである。一方には神という非合理があり、しかし人の思考は、それとは裏腹に、いたって合理的なのである。
(…)
「神という根本的な問題を棚上げにしたまま、平気で現実的であり合理的である」というのは、別に日本にだけ特殊なあり方ではなくて、それは当たり前の「近世的あり方」なのである。だからそれは、現在の世界中に当たり前にある。
「第八章 日本人の神」 p.289
太字部は引用者による
この一節だけで、世界史の意義というか、世界史とは何かがストンと腑に落ちる。
というぐらいの衝撃を僕は感じるのですが、それは別の話なのでさておき。
上の引用の先からさらに引きます。
近世というのは、そういう時代なのである。だから、「本居宣長にとって神とはいかなるものか?」という問いには、意味がない──本居宣長が『古事記』という神が実在する世界を扱っているにもかかわらず、この問いには意味がない。そう考えれば話は明快になって、『本居宣長』の後半だってもっと整理されるし、小林秀雄だって、実はその手前にまで行っているのである。しかし近代人には、そういう放擲が出来ない。
(…)
存在していて関係ない神を放擲してしまうのは、簡単なことなのである。ある意味で、驚嘆すべき時代である。人はそのように、大問題から自由であった──ということになると、「なんで日本の近世にはそんな時代が実現してしまったのか?」ということになる。かつて人は、宗教に束縛されていたにもかかわらず。
同上 p.290
斜字は引用元の傍点部
この『小林秀雄の恵み』という本は、
本居宣長を自分(=小林秀雄)に引きつけて探求した『本居宣長』という本を書いた小林秀雄を、
自分(=橋本治)に徹底的に引きつけながら同時に突き放して探求した橋本治の著書です。
「徹底的に引きつけながら同時に突き放して」の探求を、かつ自信満々に行えること、
小林秀雄という「じいちゃん」から様々な「恵み」を得ながら、
同時にある場所ではきっぱりと否定(無論、本居宣長もその対象に入る)すること、
そんな大それたことができるのは「自分の身体は頭がいい」と確信している彼ならではのこと。
ですが、それもさておき、
引用部を読んでいて、僕はつい最近読み込んだマリオンの『存在なき神』を連想しました。
「存在していて関係ない神」、ではなくてマリオンにとって神は「存在しない神」で、
つまり彼からすれば、存在はしていないが自分には大いに関係している神、のはずで、
それはどうあれ、マリオンも近代人であり、「神を放擲してしまう」ことができない。
神に関することを、人生の、あるいは人類にとっての大問題だと捉えずにはいられない。
だからこそ『存在なき神」のような難解な論理を延々と展開する必然が彼の中にあるのですが、
この本を読んでいるあいだ、僕は別の場所で鈴木大拙の『無心ということ』も併読していて、
そのあいだに、
マリオン(西洋の宗教者)と大拙(東洋の宗教者)の目指すところは一緒なのではないか、
それを論理で示すのは難しくとも、実践のうえで何がしかの共通項を見出すことは可能だろう、
というのは大拙が『無心ということ』で言ってることなんだけどね、
といったことを考えていました。
(異国語から母語への)翻訳というのは難しくて、その完全性なるものは不可能で、
でもそれは異文化理解が不可能であることと必ずしも直結するわけではなく、
「実践のレベルでは異文化理解があり得る」という可能性を、
翻訳作業そのものにこだわると見えなくなる。
という話はまた脇道ですが、
無心にせよ宗教心にせよ、個人が内で体得する難しさは、
それを複数の他者に理解(追体験)させるための表現の難しさと比べると、
どちらも大概だろうけれどその質は異なるとおもいます。
大拙の『無心ということ』は講演録なので文章は口頭調で、
頭で理解というよりは身体とか体感、体験に訴えるもので分かりやすいのですが、
それでも言葉でもって「言葉の外」を伝えようとするのだから当然わかりにくい。
「それを難解と断ずるは有心の証左」などと言われると、ほなどないすんねん、
と放り出したくもなるというものです。
論理を放擲できない者は、無心を放擲せざるを得ない。
そも、元あった無心が放擲されたのは、人が意識という論理を得たからである。
自分(という意識)が生まれたその最初から何かを得てしまった人というものは、
「何かを放擲せずにはいられない生き物」という点で動物と分かたれる。
大拙によれば、論理を放擲して無心(無分別)を得たあとに、
そのまま分別の世界に戻って来なければ木石や動物と変わらぬのであって、
分別→無分別→分別という経過ののち、俗世における無心の境地に相成る。
従って、悟りの境地とは、論理の放擲に続き、無分別も放擲せねばならぬ。
そうして、「全て見ながら何も見ず」、「全て聞きながら何も聞かない」、
などと表される無心の挙措においては、絶えず放擲が成されており、
決してこれは岩上に瞑想する行者が如く静的なプロセスではあり得ない。
一竹葉、堦を掃いて塵動かず、
月、潭底を穿ちて水に痕なし。
などと、また思いつくまま書いたのも脇道ですが、
今ちょっと調べると、「一竹葉」は「一竹影」なのですね。
『無心ということ』の表記は前者なんですが、意味としては後者で通る。
講演録の書き取り違いかもしれませんが、まあそうは考えないでおきます。
竹の葉の影が、地面に在る事物を薙ぎ払うようでありながら、
実際はその場の塵一つとして微動だにしない。
それは驚きでもあるし、認識の混濁でもありますが、
その驚き、あるいは混乱とはなにかといえば、
「影」は「竹の葉」ではないということ、ではないからです。
…すみません、思いつきが面白くて本題に戻れませんが、
『無心ということ』はここ最近に読んで、
そこから連続しての(付箋箇所の)再読もしているので、
いちど思いつくと書きたくなることが溜まっているようです。
鈴木大拙とJ・L・マリオンの話をしていたところでした。
…違うな、橋本治とマリオンですね。
まだ本記事のタイトルの話までたどり着いていませんので、続きます。
二つ目の引用の要点を並べます。
「存在していて関係ない神を放擲してしまう」
「ある意味で驚嘆すべき時代である」
「なんで日本の近代にはそのような時代が実現してしまったのか?」
『小林秀雄の恵み』の、この引用の先に、その理由が書いてあるのかもしれませんが、
(その先に書いてあることを今の僕は全く覚えていません)それはさておきます。
もしかすると、その実現の理由につながるかもしれませんが、そうでなくとも、
そのような近世という時代がいかなるものであったか、
渡辺京二の『逝きし世の面影』はそれを知る格好の書だと思いますが、
それもさておき、
「それ」を知ることは、単なる知識として得るだけでなく、
(ようやく安田登氏の『イナンナの冥界下り』のまえがきに戻ります)
「"心の時代"のその次の時代」を構想するために重要な手続きとなるだろう、
というのが、
『小林秀雄の恵み』の再読中に何かを書きたくなってしまった思いつき、
つまり本記事を書くことになった動機(を文章にしてみたもの)です。
話を順にして文章に展開していって、へえというか「ふーん」という感じなんですが、
この記事を書く前にキーワードとして思いついていたのが、タイトルです。
「近世→近代→現代(今)→現世(未来)」
現世(未来)と書いたのは、詳しくは「現世(あるべき未来)」です。
誰が「あるべき」と思うかといえば、もちろん、僕がです。
『小林秀雄の恵み』からの一つ目の引用を、下に一部再掲します。
近世という時代は、非合理かもしれない神を一方に存在させて、その残りを合理性で仕切るという時代なのだ。神という非合理の支配下にあれば中世だが、近世という時代は、かつて支配的だった神をそのままの位置に安置し、距離を置いて隔離する──だから、支配はされないのである。(…)神という非合理と、合理性を求める人とが調和的であるのは、神と人とが距離を保ちえた近世の特徴なのである。一方には神という非合理があり、しかし人の思考は、それとは裏腹に、いたって合理的なのである。
僕が考えているのは、懐古的なものではありません。
アーミッシュ的な暮らしが、現代社会において都市や街の規模で、
(あるいはそれが可能な規模でコミュニティごとに分散して、)
実現できればそれに越したことはありませんが、まあまず無理です。
ただ、過去のある時期の生活を歴史から参照することに意味があるとすれば、
それは「思想として」、その過去を現代に活かす、あるいは蘇らせることです。
ちょうど今読んでいる…違うな、
だいぶ前に鎖書として組んだセットをいくつか最近見直した中の一冊である、
『臨床とことば』(河合隼雄・鷲田清一)にあったんですが、
河合隼雄氏が心理療法で患者を治療する姿勢についての表現で(目次にもある)、
「便宜的合理性に賭ける」というものがありましたが、
たとえば、まさにこれです。
河合隼雄は、治療者として患者に対して受け身になります。
(まずは)余計な口を挟まず、相手の言うことを聴くに徹する。
誇大妄想に苦しむ患者の話にも、その人自身が基準の合理性がある。
また、その合理性には、論理の辻褄とはまた別の、切迫度も存在する。
治療者が患者に相槌を打つか、やんわり翻意を促すか、無下に否定するか、
その選択の判断基準は合理性の度合いではなく切迫度であり、
それは治療者が患者と膝突き合わせて相対せずには計れないものである。
治療者は、とにかく患者には治ってほしい。
どうして治ったか、どのような経過をたどって治療できたか、
そんなことは二の次どころか、現の治療の中ではどうでもよい。
が、それは合理性を軽視する、疑うのも、無視するのも違う。
患者の治療に徹するためのツール(機能)としての合理性、
それが「便宜的合理性」であり、
患者が同じくそうであるように、
治療者はその便宜的合理性に己の身を賭す。
「身を賭す」ことの意味の一つは、
患者に寄り添い過ぎると、治療者も同じ状況に堕ちることである。
それは、治療する時間に限らず、治療者の生活全体に影響を及ぼす。
あるいは、患者が治療した後のことを考える。
治療が終わるとは、患者が自分の意思で通院を止めることである。
まず、その治療の終わりまでに要した時間に、意味はない。
三日で鬱が治ったと自己判断した患者が、
その後何年もの間、自覚を欠いた鬱症状に悩まされることもある。
また、治療が終わっても、かさぶたが取れて元通り、とは限らない。
鬱に悩んだ学生が、その治療の過程で、将来の進路を変えたとする。
治療によって手にした別の未来が、その学生にとって良かったかどうか。
自分の意志を不屈に貫けるようになって、戦いと挫折の続く人生と、
鬱を抱えたまま、消極的ながら小さな平和を守り続ける人生と、
どちらが彼にとって幸福な人生であったか。
そんなことは彼にも分からないし、もちろん治療者にも分からない。
つまり、便宜的合理性に賭けた治療そのものが便宜的ということです*1。
合理性の機能とは、そもそもが便宜です。
合理の便宜性は便宜にある、といってもいい。
便宜を放擲しての合理性の追求は、悪しき手段の目的化なのです。
思い切って飛躍すれば、「心の時代」における不安の蔓延はその結果ともいえる。
神は、神的なものは、
決して人間の手に届かない対象としての神は、
必要である。
とマリオンは『存在なき神』に書いていました。
神は非合理である。
たしかに。
しかし「神は非合理である」と言うのは、合理性であり、近代的知性である。
無論、現代的知性も同じ。
心の時代の「次」は、これを超えなければならない。
それは同時に、思想的な意味で、近世を呼び醒ますものでもある。
だから、(単に字面の上でということですが、)
「現代」の次に来るべきは「現世」である、
というのが、タイトルの意味です。
この「現世」は、あるいは神のようなものでもある。
何せ、決して届かないもの、決して到達しない時代だからです。
けれど、それを目指すことが無意味ということにはならない。
それを無意味と言うのは、
近世を生きた人々の人生がことごとく無意味であったと言うようなものです。
というか、
それを「無意味であった」と断じて疑わないのが、現代の合理性なのです。
しかも、(論理的に辿れば真なのに、それに目を向けないことで)自覚なく。
これはいつも書いている話ですが、
現代人がその合理性を乗り越えるためには、
合理性から距離をおいて無関心でいるのは間違いで、
その合理性に一度、徹底的に全身を浸さねばなりません。
「西洋人には武士道はわからない」と豪語する現代の日本人が、
それをよく学べるのはオイゲン・ヘリゲル(『弓と禅』)からである。
このことはもう何世代も前から認識されていたことですが、
たとえば、そのようなことです。
一言で抽象化すればそれは「自己言及を掘り下げる」ことで、
だとすると、あるいは、
ニコラス・ルーマンも「現世」へ向かうキーマンの一人かもしれませんが、
現代人が得意とするのは、
その真逆の機能を発揮するものとしての「自己参照」ですね。
自己言及、自省、自覚、といったものは、
個人では行えるが集団としてまとまりを持って遂行するのは難しい、
とは自分が本を読むようになってだんだんと気付いてきたことですが、
それと、
かの「自己参照」つまりは、
個人や部族内の自画自賛と外部への無関心(感受性の低下)の相乗、
といったものが個人に留まらず集団(集団内、集団間)に感染しやすいこととは、
不幸の内実には多様性があるが幸福のそれは単調にして凡庸である、
という観察と対照を成すのではないか、
と今ふと思いつきました。
「幸福」も「不幸」も観察的定義であって、
「自分が幸福か不幸かを問わないでいられる状況を幸福と呼ぶ」
という自己言及的定義を真とするなら、
まあそうなのでしょう。
× × ×